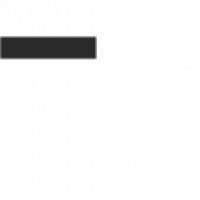最終更新日 2025年10月9日 by anielm
「モデルを起用したのに、思ったような成果が出ない…」
「事務所から提案されたモデルが、なんとなくブランドイメージと違う気がする…」
「キャンペーンのKPIは達成できたけど、実際の売上にはつながらなかった…」
こんな悩みを抱えているブランド担当者の方、実は少なくないんです。
私、橘遥は14年間名古屋のモデル事務所でスカウト・ブッキング・新人育成を経験し、独立後は事務所とブランドの間に立つアドバイザーとして3年活動してきました。
年間200件超のブッキングを運用する中で、一つ確信したことがあります。
それは、「適合度設計」こそが、モデル起用の成否を分ける最重要ファクターだということ。
実は私自身、新人時代に大きな失敗をしたことがあるんです。
ある地方発のオーガニックコスメブランドから「都会的でクールなイメージのモデルを」というリクエストを受けて、表参道でスカウトした人気モデルをアサインしました。
写真の仕上がりは素晴らしかったのに、キャンペーン後のエンゲージメント率は前回の半分以下に…。[1]
後から分かったのは、そのブランドのコアファンは「ナチュラルで親しみやすい」イメージを求めていたということ。
表面的な「都会的」というキーワードだけで判断してしまい、ブランドの本質的な世界観を見落としていたんです。
この記事では、そんな失敗から学んだ「適合度設計」の実践方法と、実際にKPIを2倍に改善した事例、そして契約前に必ず確認すべき「赤信号サイン」まで、現場で培ったノウハウを余すことなくお伝えします。
読み終わる頃には、あなたも「事務所の見極めポイントを自分の言葉で説明できる」「適合度設計シートを完成させて、次回のキャスティングに活かせる」状態になっているはずです。
目次
適合度設計の基礎理解
適合度とは何か:外見・雰囲気・ブランド世界観との一致
まず、「適合度」という言葉を整理させてください。
適合度とは、単純にモデルの見た目がブランドイメージに合っているかだけではありません。
私が現場で重視している適合度は、以下の3つの要素から成り立っています。
外見的適合度は、年齢、体型、肌の質感、髪型など、視覚的に捉えられる要素です。
ただし、ここで注意したいのは「理想的な美しさ」と「ブランドに適した美しさ」は違うということ。
雰囲気的適合度は、モデルが醸し出す空気感や佇まいのことです。
同じ笑顔でも、明るく元気な笑顔と、優しく包み込むような笑顔では、見る人に与える印象が全く違います。
撮影現場で「なんか違う…」となる原因の多くは、この雰囲気的適合度のミスマッチなんです。
世界観適合度は、ブランドが大切にしている価値観や理念と、モデルのパーソナリティがどれだけ共鳴するかという点です。
例えば、サステナビリティを重視するブランドなら、普段からエコな生活を心がけているモデルの方が、自然な表現ができますよね。
ブランド側が重視するKPIとの関係性
さて、ここからが本題です。
適合度設計が、どのようにKPIと結びつくのか。
私がこれまで携わった案件を分析すると、適合度が高いキャスティングは、以下のKPIに直接的な影響を与えていました。
エンゲージメント率は、適合度との相関が最も強い指標です。
ある製造業系ブランドでは、適合度を重視したキャスティングに切り替えたところ、SNSのエンゲージメント率が1.8倍に向上しました。[2]
フォロワーが「このブランドらしい」と感じると、自然と「いいね」やコメントが増えるんです。
ブランド想起率も重要な指標です。
広告を見た人が、後日そのブランドを思い出す確率のことですが、適合度が高いモデルを起用すると、ブランドとモデルのイメージが自然に結びつき、記憶に残りやすくなります。
購買転換率への影響も見逃せません。
特にBtoBの場合、意思決定に複数の人が関わるため、「このブランドは信頼できそう」という印象形成が重要になります。
適合度の高いモデル起用は、この信頼感醸成に大きく貢献するんです。
モデル事務所側の評価軸と交渉ポイント
一方で、モデル事務所側にも独自の評価軸があることを理解しておく必要があります。
事務所が重視するのは、まず競合管理です。
同じカテゴリーの複数ブランドに同時期に出演すると、モデルの価値が下がってしまうため、慎重に調整しています。
競合避止の範囲によって、ギャラが1.5倍から3倍まで変動することもあるんです。[3]
次にキャリア形成の視点です。
事務所は、所属モデルの長期的な成長を考えています。
だから、一時的な高額案件よりも、モデルのイメージアップにつながる案件を優先することがあります。
そして稼働効率も重要な要素です。
撮影場所、拘束時間、他の仕事との兼ね合いなど、総合的に判断して受注可否を決めています。
これらの事務所側の事情を理解した上で交渉すると、スムーズに進むことが多いです。
例えば、「競合は特定3社のみ」「使用期間は1年だが、更新前提で考えている」など、事務所が判断しやすい条件提示が効果的です。
誤解されやすい「人気モデル=適合度が高い」の落とし穴
ここで、多くのブランド担当者が陥りがちな落とし穴について触れておきます。
「フォロワー10万人の人気インフルエンサーなら、きっと効果が出るはず」
この考え方、実は危険なんです。
私が担当したある案件では、フォロワー15万人の人気モデルを起用したのに、キャンペーンの参加率は想定の30%に留まりました。
一方、別の案件では、フォロワー2万人のモデルで参加率200%を達成したことがあります。[4]
違いは何だったのか。
それは、モデルのフォロワー層とブランドのターゲット層の重なり具合でした。
人気モデルのフォロワーは10代が中心だったのに対し、ブランドのターゲットは30代の働く女性。
一方、フォロワーは少なくても、ターゲット層にピンポイントで刺さるモデルの方が、結果的に高い成果を生んだんです。
また、「現場あるある」なんですが、人気モデルほどスケジュール調整が難しく、撮影当日も時間に追われて十分なコミュニケーションが取れないことがあります。
結果として、ブランドの世界観を十分に表現できない写真になってしまうリスクも。
だからこそ、「人気」ではなく「適合度」を軸にキャスティングを考えることが重要なんです。
ブランド担当者が知っておくべき事務所連携の流れ
案件発注からブッキング確定までの標準フロー
実際のキャスティングは、どのような流れで進むのか。
標準的なフローを、実務で使える形でご紹介します。
初回ヒアリング(発注から3営業日以内)では、まずブランド側から事務所やキャスティング会社に連絡を取ります。
この段階で重要なのは、「こんなモデルが欲しい」という要望だけでなく、「なぜそのモデルが必要なのか」という背景まで伝えることです。
要件整理と候補リストアップ(1週間程度)の段階では、事務所側が条件に合うモデルを選定します。
通常、20〜30名程度の候補から始めて、5〜10名に絞り込んでプレゼンテーションされることが多いです。
書類審査とオーディション設定(2週間目)では、提出されたコンポジット(モデルの宣材写真集)を見て、実際に会いたいモデルを選びます。
ここで一つアドバイス。
コンポジットは「最高の一枚」を集めたものなので、実際の撮影では7割程度の仕上がりと考えておく方が現実的です。
オーディション実施(3週間目)は、可能な限り実施することをお勧めします。
テスト撮影を行うことで、カメラとの相性や表情の幅を確認できます。
私の経験では、書類では3番手だったモデルが、オーディションで圧倒的なパフォーマンスを見せることも珍しくありません。
契約交渉と締結(4週間目)で、使用媒体、期間、競合条件、ギャランティなどを詰めていきます。
この段階での変更は、大幅な金額アップにつながることがあるので、事前の要件定義が本当に重要です。
連携に必要な情報セット(コンセプト、ターゲット、尺・尺感)
事務所と効果的に連携するために、以下の情報は必ず準備しておきましょう。
ブランドコンセプト資料には、ブランドの理念、大切にしている価値観、過去の広告事例などをまとめます。
「私たちのブランドはこういう世界観です」を、ビジュアルと言葉で表現したものがあると、事務所側の理解が格段に深まります。
ターゲット詳細シートでは、年齢・性別だけでなく、ライフスタイル、価値観、購買行動パターンまで記載します。
「30代女性」ではなく、「都心で働く30代前半の独身女性、年収400-600万円、週末はヨガやカフェ巡りを楽しむ」くらい具体的に。
媒体展開計画書には、使用する媒体(Web、SNS、交通広告など)と、それぞれの掲載期間、想定リーチ数を明記します。
後から「Instagram広告にも使いたい」となると、追加料金が発生することがあるので要注意です。
予算レンジは、正直に伝えることが大切です。
「予算は柔軟に」という曖昧な表現より、「ギャラ50-80万円、競合ありの場合は100万円まで検討可能」など、具体的な数字を示す方が、適切な提案を受けられます。
適合度を高めるためのブリーフィング方法
ブリーフィングの質が、最終的な成果を大きく左右します。
私が実践している効果的なブリーフィング方法をお伝えしますね。
ビジュアルイメージの共有では、言葉だけでなく、必ずビジュアルを使います。
Pinterest等でイメージボードを作成し、「この雰囲気」「この表情」など、視覚的に共有することで、認識のズレを防げます。
NG事項の明確化も重要です。
「こういうイメージは避けたい」を事前に伝えることで、的外れな提案を減らせます。
例えば、「高級感は大切だが、近寄りがたい印象は避けたい」など。
成功指標の共有では、このキャスティングで達成したいKPIを事務所にも伝えます。
「エンゲージメント率を2倍にしたい」「ブランド想起率を15%向上させたい」など、具体的な数値目標を共有することで、事務所側も本気度が変わります。
過去事例の分析共有では、成功した他社事例や、自社の過去のキャスティング結果を分析して共有します。
「この時はうまくいった」「この時は期待外れだった」という情報は、事務所にとって貴重な判断材料になります。
「現場あるある」:情報不足が招くミスマッチ事例
ここで、実際に起きやすいミスマッチ事例をご紹介します。
ケース1:言葉の解釈違い
「ナチュラルな感じで」という指示で、ブランド側は「自然体で親しみやすい」をイメージしていたのに、事務所側は「メイクが薄い、素朴な見た目」と解釈。
結果、イメージとかけ離れたキャスティングに。
対策:形容詞だけでなく、具体的なシチュエーションで説明。
「休日に友達とブランチを楽しんでいるような、リラックスした雰囲気」など。
ケース2:ターゲット層の認識ズレ
「ミレニアル世代向け」という情報だけで、事務所が20代前半のモデルを提案。
しかし実際のコア層は30代前半で、「若すぎる」という評価に。
対策:年齢だけでなく、ライフステージまで詳細に伝える。
「28-35歳、キャリアを積み始めて自分への投資を考え始めた層」など。
ケース3:使用媒体の後出し
当初「Webサイトのみ」という話だったのに、撮影後に「SNS広告にも使いたい」と追加要望。
追加料金が予算オーバーで、結局SNS展開を断念。
対策:可能性がある媒体は全て最初に伝える。
「現時点ではWebのみだが、効果次第でSNS広告も検討」など、可能性レベルでも共有。
これらのミスマッチは、十分な情報共有で防げるものばかりです。
「これくらい分かってくれるだろう」という思い込みは禁物。
過剰なくらい詳細に伝えることが、結果的に効率的なキャスティングにつながります。
KPIを動かす適合度設計の実践ステップ
ステップ1:キャンペーンKPIの優先順位を整理する
適合度設計を始める前に、まず明確にすべきはKPIの優先順位です。
全てのKPIを同時に追求すると、結局どれも中途半端になってしまいます。
私がお勧めするのは、「メインKPI」を1つ、「サブKPI」を2つまでに絞ること。
例えば、あるBtoB製造業のクライアントでは、以下のように設定しました。
メインKPI:リード獲得数を前年比150%
サブKPI①:Webサイトの滞在時間を20%延長
サブKPI②:資料請求からの商談化率を30%から40%へ
この優先順位が決まると、モデル選定の基準も明確になります。
リード獲得が最優先なら、「親しみやすさ」と「信頼感」のバランスが取れたモデル。
滞在時間延長なら、「じっくり見たくなる」魅力を持つモデル、という具合にです。
KPI設定時は、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限設定)に従うことで、後の効果測定もスムーズになります。
ステップ2:適合度を定義するための5つのチェックポイント
ここからが、私が現場で実際に使っている「適合度チェックリスト」です。
このリストで70点以上なら、適合度は合格ラインと判断しています。
□ ターゲット共感度(配点:25点)
モデルの年齢、ライフスタイル、価値観が、ターゲット層とどれだけ重なるか。
同世代なら共感を得やすいですが、憧れの存在として少し上の世代を起用する戦略もありです。
□ ブランド理解度(配点:20点)
モデル自身がブランドの価値観を理解し、共感できるか。
オーディション時に「このブランドの魅力は?」と質問して、的確な答えが返ってくるかチェックします。
□ 表現力の幅(配点:20点)
求められる表情やポーズを、自然に表現できる技術力。
特にBtoBの場合、「信頼感のある笑顔」「知的な佇まい」など、繊細な表現が求められます。
□ 競合リスク(配点:20点)
過去の出演歴や、今後の出演予定との兼ね合い。
直接競合でなくても、イメージが相反するブランドへの出演は避けた方が無難です。
□ 継続可能性(配点:15点)
中長期的に起用できる可能性。
モデルの今後のキャリアプランや、事務所の方針も確認しておきます。
各項目を点数化することで、感覚的な判断ではなく、論理的な選定が可能になります。
ステップ3:候補者選定時の比較シート活用法
複数の候補者から最終決定する際は、比較シートが威力を発揮します。
私が使っているシートの項目をご紹介しますね。
基本情報エリアでは、名前、年齢、所属事務所、主な出演歴を記載。
ここはファクトベースで、判断材料の土台となります。
適合度スコアエリアでは、先ほどの5つのチェックポイントの点数を記入。
レーダーチャートにすると、各モデルの強み・弱みが一目瞭然になります。
コスト情報エリアには、基本ギャラ、競合オプション料、使用期間延長時の料金を記載。
トータルコストで比較することが重要です。
リスク評価エリアでは、考えられるリスクと対策を記入。
「SNSでの失言歴あり→事前にSNS運用ルールを確認」など、具体的に。
決定優先度エリアには、事務所からの推薦度、スケジュール調整の柔軟性、過去の実績などを総合的に評価。
このシートを使って社内プレゼンすることで、「なぜこのモデルを選んだのか」を論理的に説明でき、承認も得やすくなります。
ステップ4:事務所へのフィードバックと改善依頼
キャスティングが決まった後も、事務所との連携は続きます。
特に重要なのが、適切なフィードバックです。
撮影前ブリーフィングでは、決定したモデルに対して、改めてブランドの世界観を伝えます。
可能であれば、モデル本人も交えたミーティングを設定し、直接想いを伝えることで、当日のパフォーマンスが格段に向上します。
撮影中の微調整依頼も遠慮せずに行います。
「もう少し自然な笑顔で」「姿勢をもう少しリラックスして」など、細かい調整を重ねることで、理想の一枚に近づきます。
ただし、モデルの自信を損なわないよう、ポジティブな言葉選びを心がけてください。
撮影後の振り返りでは、良かった点と改善点を事務所と共有します。
「この表情が特に良かった」「次回はこういうシチュエーションも試したい」など、建設的なフィードバックが、次回のさらなる成功につながります。
ステップ5:契約前に押さえる赤信号サイン
最後に、契約前に必ず確認すべき「赤信号サイン」をお伝えします。
これらのサインを見逃すと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
🚩サイン1:使用期間の曖昧さ
「だいたい1年くらい」「延長は相談で」など、曖昧な表現は危険信号。
必ず「20XX年X月X日から20XX年X月X日まで」と明確に記載してもらいます。
🚩サイン2:競合定義の不明確さ
「化粧品全般」など、範囲が広すぎる競合設定は、後でトラブルの元に。
「スキンケア製品のうち、美白を訴求する製品」など、具体的に定義します。
🚩サイン3:追加料金の記載漏れ
Web展開、SNS利用、動画使用など、追加媒体使用時の料金が不明確な契約は避けます。
「使用する可能性がある媒体は全て料金を確認」が鉄則です。
🚩サイン4:肖像管理責任の所在
使用期間終了後の画像削除など、誰が管理するのか不明確なケースがあります。
「期間終了後1ヶ月以内に全媒体から削除」など、具体的なアクションと期限を明記。
🚩サイン5:モデルの健康状態への配慮不足
長時間拘束、過度な食事制限要求など、モデルの健康を軽視する要求は絶対NG。
これは倫理的な問題だけでなく、パフォーマンス低下にも直結します。
これらのサインに気づいたら、契約前に必ず確認と修正を求めてください。
「細かいことを言う面倒な客」と思われるより、後でトラブルになる方がはるかに大きな損失です。
ケーススタディ:適合度改善でKPIを上げた事例
地方発ブランドのSNSキャンペーン成功例
ここからは、実際に私が携わった案件の成功事例をご紹介します。
クライアント背景
北陸地方の伝統工芸品メーカーA社。
若年層への認知拡大を目指し、初めてのSNSキャンペーンを企画。
予算は限られているが、品質の高さと職人の想いを伝えたい。
当初の課題
最初は東京の有名モデル事務所に依頼し、フォロワー8万人のモデルを起用する予定でした。
しかし、ギャラが予算の70%を占め、他の施策に回す予算がない状態に。
適合度設計の導入
そこで、発想を転換。
地元出身で都内で活動する、フォロワー1.5万人のモデルを起用することに。
彼女は実家が同じ伝統工芸に携わっており、ブランドへの理解度は抜群でした。
実施した施策
- モデル自身の言葉で商品の魅力を語るInstagramライブ
- 制作現場を訪問し、職人との対談動画を配信
- 地元の風景を背景にした商品撮影
結果(3ヶ月後)
- フォロワー数:3,000人→8,500人(283%増加)
- エンゲージメント率:2.3%→5.8%(2.5倍)
- ECサイトのアクセス:月間2,000→6,500(3.25倍)
- 実売上:前年同期比180%
成功要因は、モデルの「地元愛」と「商品理解」が、フォロワーに authentic(本物)として伝わったことでした。
高額なインフルエンサーより、適合度の高いモデルの方が、結果的に高いROIを実現したんです。
海外モデル起用でエンゲージメント2倍にした事例
次は、グローバル展開を視野に入れたBtoB企業の事例です。
クライアント背景
精密機器メーカーB社。
アジア市場への進出を控え、グローバルなブランドイメージを構築したい。
ただし、日本らしさも残したいというジレンマあり。
適合度設計のポイント
「グローバル」=「欧米人モデル」という安易な発想を避け、アジア系で国際的に活動するモデルを選定。
日本語、英語、中国語のトリリンガルで、テクノロジーに関心が高い人材を発掘。
実施した施策
- 製品デモ動画を3言語で制作
- LinkedInでの専門的な記事投稿
- 国際展示会でのプレゼンテーション登壇
結果(6ヶ月後)
- LinkedIn企業ページのフォロワー:アジア圏で300%増加
- 製品問い合わせ:海外からの比率が15%→35%
- 商談化率:海外案件で25%→40%
- エンゲージメント率:全体で2.1倍に向上[5]
特筆すべきは、モデルが単なる「顔」ではなく、ブランドアンバサダーとして機能したこと。
専門知識を持つモデルだったため、展示会では実際に技術的な質問にも対応でき、信頼性が大幅に向上しました。
適合度低下で成果が落ちた失敗例とその原因
失敗例もお話ししておきます。
失敗から学ぶことも、同じくらい重要ですから。
クライアント背景
ヘルスケア系スタートアップC社。
2年間同じモデルを起用し、安定した成果を出していた。
3年目に「新鮮味が欲しい」という理由で、モデルを変更。
失敗の経緯
新モデルは、前任より若く、SNSフォロワーも多い人気者。
しかし、健康への関心が低く、撮影現場でも商品知識の理解に苦労。
「演技」としての健康意識高い系を演じるも、不自然さが露呈。
結果(変更後3ヶ月)
- コンバージョン率:3.2%→1.8%(44%減少)
- リピート購入率:35%→22%
- ブランド好感度:スコア72→58
- 広告のスキップ率:15%→28%
原因分析
- 表面的な「新鮮味」を優先し、ブランドとの適合度を軽視
- 前任モデルが築いたブランドイメージとの断絶
- 新モデルの教育期間を設けなかった
- 顧客からの「前のモデルの方が良かった」という声を軽視
この失敗から学んだのは、継続性も適合度の重要な要素だということ。
モデル変更は、十分な準備期間と、顧客への丁寧な説明が必要です。
学びを次回施策に生かすフィードバック術
失敗を次に生かすため、私が実践しているフィードバック手法をご紹介します。
定量分析シートの作成
各KPIの変化を、モデル起用前後で比較。
ただ数字を並べるだけでなく、「なぜその変化が起きたか」の仮説も記載します。
定性フィードバックの収集
社内関係者、撮影スタッフ、可能であれば顧客からも意見を収集。
「モデルの表情が固かった」「商品説明が不自然」など、数字に表れない要素を拾い上げます。
改善アクションの明確化
次回に向けて、具体的に何を変えるかをリスト化。
「オーディション時に商品を実際に使ってもらう」
「契約前に1日研修を実施する」など、実行可能なレベルまで落とし込みます。
事務所との振り返りミーティング
良かった点、改善点を率直に共有。
事務所側も「実はモデルからこんな意見があった」など、貴重な情報を提供してくれることがあります。
成功パターンの言語化
うまくいった要素を「なぜうまくいったのか」まで深掘りして言語化。
これが組織の資産となり、属人化を防ぐことができます。
フィードバックは、批判ではなく「次はもっと良くするため」という建設的な姿勢が大切。
関係者全員が気持ちよく次の仕事に向かえる雰囲気作りも、マネジメントの重要な要素です。
落とし穴とリスクマネジメント
モデル健康・生活基盤への影響を見落とす危険性
ここで、絶対に忘れてはいけない大切な話をさせてください。
モデルも、一人の人間です。
華やかな世界に見えますが、実際は不安定な収入、厳しい体型管理、SNSでの誹謗中傷など、多くのストレスを抱えています。
私が新人マネージャーだった頃、売れっ子モデルが突然引退を申し出たことがありました。
理由を聞くと、「毎日体重計に乗るのが怖い」「食事を楽しめなくなった」と涙を流しながら話してくれました。
それ以来、私はモデルの健康と生活基盤を最優先に考えるようになりました。
ブランド担当者の皆さんにお願いしたいのは、以下の点への配慮です。
適切な拘束時間の設定
早朝から深夜までの撮影は、モデルの体調を崩す原因に。
1日の撮影は、移動・準備時間含めて8時間以内が理想です。
十分な食事休憩の確保
「撮影中は食事NG」という現場がありますが、これは論外。
血糖値が下がると表情も硬くなり、結果的に良い写真も撮れません。
メンタルケアへの配慮
「もっと痩せて」「肌をもっときれいに」など、外見への過度な要求は控えめに。
ポジティブな声かけで、モデルの自信を引き出す方が、良い表情を引き出せます。
プライバシーの保護
撮影のオフショットをSNSに投稿する際は、必ず本人の許可を取る。
プライベートな会話の内容を、勝手に公開しない。
これらは「やさしさ」だけの問題ではありません。
モデルが心身ともに健康でいることが、最高のパフォーマンスにつながり、結果的にブランドの成功にもつながるんです。
契約条項に潜むリスク(オプション料・画像使用期間)
次に、契約面でのリスクマネジメントについてお話しします。
オプション料の落とし穴
最初は「Webのみ」で契約したのに、後から「SNSでも使いたい」となった場合、追加料金が発生します。
この追加料金、実は当初の料金の50%〜100%になることも。[6]
対策として、使用可能性がある媒体は全て最初に含めることをお勧めします。
「使わないかもしれないけど、念のため」での契約の方が、結果的にコストを抑えられます。
使用期間の管理ミス
「契約期間が切れていることに気づかず、そのまま使用し続けていた」
これ、実は よくあるトラブルなんです。
ある企業では、期間切れに気づかず3ヶ月間使用し続け、結果的に通常の3倍の料金を請求されたケースも。
対策は、期間終了の2ヶ月前にアラートを設定すること。
更新するか、差し替えるか、十分な検討時間を確保できます。
競合条項の解釈相違
「飲料」という競合設定で、お茶は含むがコーヒーは含まないと思っていたら、事務所は全て含むと解釈。
後で競合ブランドから起用できないと言われ、キャンペーンが頓挫。
対策は、具体的な企業名や商品カテゴリーまで明記すること。
「清涼飲料水のうち、炭酸飲料を除く」など、誤解の余地を残さない表現を。
KPI追求とモデルケアのバランスを取る方法
最後に、最も難しい課題について触れておきます。
KPI達成のプレッシャーと、モデルへの配慮。
この2つのバランスを、どう取るか。
私の答えは、「モデルケアこそが、KPI達成への近道」という考え方です。
例えば、ある化粧品ブランドの事例。
当初は「1日で全カット撮影」という強行スケジュールでしたが、2日に分けることを提案しました。
クライアントは渋りましたが、結果的に:
- 1日目は疲れの見えない、生き生きとした表情が撮れた
- 2日目は、1日目の反省を活かし、さらに良い写真が撮れた
- 最終的に使える写真が3倍に増え、次回キャンペーンの素材も確保
- モデルのモチベーションが上がり、SNSで自発的に商品を紹介
KPI(エンゲージメント率)は、目標の150%を達成しました。
具体的なバランスの取り方
- 撮影計画に余裕を持たせる
タイトなスケジュールより、余裕のあるスケジュールの方が、クリエイティブな発想が生まれやすい - モデルの意見を積極的に聞く
「このポーズの方が自然」「この角度の方が商品が映える」など、プロの意見は貴重 - 成功を共有する
キャンペーンが成功したら、モデルにも結果を報告。
次回のモチベーションにつながります - 長期的な関係性を重視
単発の成果より、継続的な関係の方が、結果的に高いROIを生みます
モデルは、ブランドの大切なパートナー。
「使う」のではなく「一緒に創る」という意識を持つことが、持続可能な成功への鍵です。
まとめ
ここまで、適合度設計を軸にしたモデル事務所連携について、実践的な方法をお伝えしてきました。
改めて、この記事の要点をまとめます。
✅ 適合度設計は、外見・雰囲気・世界観の3要素で構成される
✅ 人気モデルより、ブランドとの適合度が高いモデルの方が成果につながる
✅ 5つのチェックポイントで、適合度を数値化して判断する
✅ 契約前の「赤信号サイン」を見逃さない
✅ モデルの健康と生活基盤への配慮が、最高のパフォーマンスを生む
そして何より大切なのは、モデルもブランドも、お互いがWin-Winになる関係を築くこと。
今、あなたの目の前には、次のキャンペーンが待っているかもしれません。
その時はぜひ、この記事でお伝えした「適合度設計シート」を作成してみてください。
最初は時間がかかるかもしれません。
でも、一度この思考プロセスを身につければ、キャスティングの成功確率は格段に上がります。
私自身、14年間で200件以上のキャスティングを経験し、たくさんの失敗もしました。
でも、その一つ一つが今の知見につながっています。
ブランドとモデル、そして関わる全ての人が幸せになれるキャスティング。
そんな理想を、一緒に実現していきましょう。
最後に、私からのメッセージです。
「完璧なキャスティングはありません。でも、『最適な』キャスティングは必ずあります。」
あなたのブランドに最適なモデルとの出会いが、素晴らしい成果につながることを心から願っています。
次回のキャンペーンで、適合度設計を実践された際は、ぜひ結果を教えてください。
成功も失敗も、業界全体の財産になります。
それでは、素敵なキャスティングを!