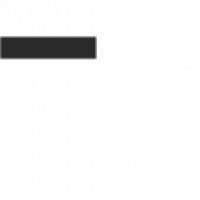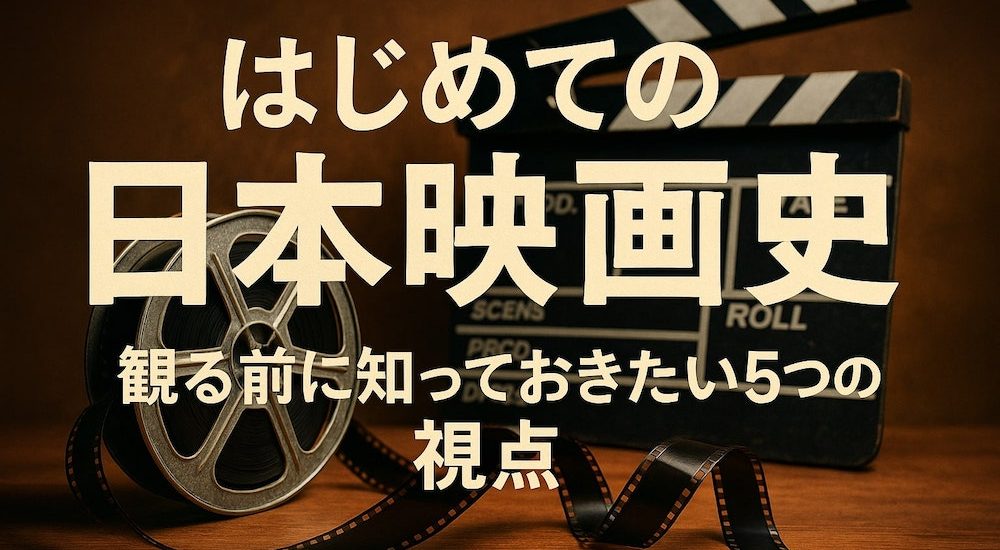最終更新日 2025年8月14日 by anielm
日本映画を観ようと思い立ったとき、どこから手をつけるべきか迷うことがあるだろう。
1世紀以上の歴史を持つ日本映画には膨大な作品群があり、その全貌を掴むのは容易ではない。
しかし、歴史を知ることは作品をより深く理解する手がかりとなる。
映画とは単なる娯楽ではなく、時代の空気を映し出す鏡であり、社会の記憶装置でもあるからだ。
私がキネマ旬報社の編集者として黒澤明や市川崑といった巨匠たちと対峙した経験から言えるのは、「観る前に知る」という姿勢が映画体験を何倍も豊かにするということである。
本稿では、日本映画を理解するための5つの視点を紹介したい。
これらの視点は、初めて日本映画に触れる人にとっても、すでに多くの作品を観ている人にとっても、新たな発見をもたらすだろう。
目次
視点1:物語としての映画史──時代背景を読む
日本映画の歴史は、そのまま近現代日本の社会変容の物語でもある。
作品を観る際には、その映画がいつ、どのような時代背景のもとで作られたのかを意識することで、単なるストーリーの先にある意味が見えてくる。
戦前・戦中・戦後という大きな区分は、映画を読み解く基本的な座標軸となる。
戦前・戦中の映画とその社会的役割
日本で最初の映画撮影は1898年、浅野四郎による『化け地蔵』『死人の蘇生』とされている。
初期の日本映画は歌舞伎の演目を中心とした「活動写真」として発展し、京都の横田商会が時代劇映画を手がけたことで産業の礎が築かれた。
この時期の映画は新しい娯楽として急速に普及していったが、戦争の影が色濃くなるにつれ、次第に国策への協力を強いられるようになる。
1930年代後半から敗戦までの映画は、国家統制のもとで製作された propaganda(宣伝)としての側面が強く、戦意高揚や国民教化を目的とした作品が増えていった。
日活は1942年に東宝に吸収合併され、映画産業は東宝、松竹、大映の3社体制に再編成された。
この時代の作品を観るときには、表現の自由が制限された状況下で、監督たちがどのように自分の芸術性を保とうとしたかに注目すると興味深い。
焼け跡からの復興と”黄金時代”の光と影
敗戦後、GHQによる占領下で日本映画は検閲されながらも、新たな息吹を取り戻していく。
1950年代に入ると、黒澤明の『羅生門』(1950年)がヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、日本映画が世界に認められる契機となった。
この時期は日本映画の黄金時代と呼ばれ、年間の映画観客動員数は10億人を超え、国民的娯楽として映画が親しまれた。
戦争の記憶を反映した作品も多く制作され、関川秀雄の『きけ、わだつみの声』(1950年)や今井正の『ひめゆりの塔』(1953年)、市川崑の『ビルマの竪琴』(1956年)などは、戦争体験の悲壮さや感傷的回顧を描いた作品として大きな社会的影響を与えた。
一方で、戦前には考えられなかった表現も可能となり、明治天皇を演じる作品が登場するなど、社会意識の変化も映画に反映されていった。
黄金時代の映画を観る際には、敗戦という国家的トラウマからの再生と、高度経済成長へと向かう社会の変容を背景に置くことで、作品の奥行きがより理解できるだろう。
高度経済成長とニューシネマの胎動
1960年代に入ると、テレビの普及によって映画観客は減少し始め、映画産業は大きな転換期を迎える。
日活が経営難に陥り、1971年から「日活ロマンポルノ」を開始したのもこの流れの中にある。
一方で、大島渚や吉田喜重、篠田正浩といった「松竹ヌーベルバーグ」と呼ばれる新世代の監督たちが台頭し、既存の映画様式に挑戦する実験的な作品が生まれた。
高度経済成長の影で取り残された人々や、急速な近代化がもたらす矛盾を描いた作品は、時代の批評としての映画の役割を示している。
この時代の映画を観るときは、経済発展と引き換えに失われつつあった何かを探る視点を持つことで、作品の問題意識がより鮮明に見えてくる。
日本映画を時代背景から読み解くための3つのポイント
- 1. 製作年を確認する
戦前か戦後か、どの社会状況下で作られたのかを意識する - 2. 同時代の社会問題を調べる
当時の観客にどのように受け止められたかを想像する - 3. 現在との関連性を考える
時代を超えて共鳴するテーマは何かを検討する
視点2:作家主義で捉える巨匠たち
「作家」としての映画監督という概念は、1950年代のフランスで生まれた「作家主義(オーテル理論)」に基づくものだが、日本映画においても、監督の個性や映像文法、主題への一貫したアプローチに注目することで、作品理解は格段に深まる。
日本映画史を代表する巨匠たちの視点や美学を知ることは、日本映画を「読む」ための重要な鍵となる。
黒澤明、市川崑、小津安二郎──映像に宿る思想
日本を代表する三大巨匠として、黒澤明、小津安二郎、溝口健二の名が挙げられることが多いが、市川崑もまた独自の映像美学で国際的に高く評価された監督である。
黒澤明(1910-1998)は、ダイナミックな画面構成と人間ドラマの融合によって、「七人の侍」(1954)や「用心棒」(1961)など、海外でも広く愛される作品を生み出した。
彼のパンフォーカス(遠近両方にピントを合わせる撮影法)を駆使した手法は、特に西部劇に影響を与え、「荒野の七人」などのリメイクを生んだ。
小津安二郎(1903-1963)は、独特の低い位置からの固定カメラワークと厳密な構図で知られ、家族の解体や世代間の葛藤をテーマに「東京物語」(1953)をはじめとする傑作を残した。
「小津調」と呼ばれる独自の映像言語は、ヴィム・ヴェンダースやホウ・シャオシェンなど、世界の映画作家に多大な影響を与えている。
市川崑(1915-2008)は、アニメーターとしてのキャリアから出発し、緻密な映像設計と斬新な切り口で「ビルマの竪琴」(1956)「鍵」(1959)など国際的に評価された作品を手がけた。
彼の映像は美しい構図と色彩感覚が特徴で、「東京オリンピック」(1965)の記録映画でも独創的な映像表現を見せている。
監督という”語り手”の個性と時代との対話
巨匠たちの作品を観る際に重要なのは、個々の監督がどのような問題意識を持ち、時代とどう対話していたかを理解することだ。
黒澤明は武士道精神や人間の尊厳を問い続け、社会正義への強い信念を作品に反映させた。
彼の映画に登場する主人公たちは、しばしば既存の社会秩序と対峙し、自らの信念を貫こうとする。
小津安二郎は、近代化する日本社会における家族の変容を静かに見つめ、伝統と変化の狭間にある人々の姿を描き続けた。
彼の作品では、「東京」が伝統と現代の衝突の場として象徴的に描かれることが多い。
市川崑は時に実験的なアプローチで、人間の内面や官能性、社会の矛盾を視覚的に表現した。
「東京オリンピック」のような記録映画においても、単なる記録を超えた芸術性を追求した点に彼の作家性が表れている。
評論家として彼らと向き合った記憶から
私がキネマ旬報社の編集者時代に接した巨匠たちの印象は、今もなお鮮明に記憶に残っている。
黒澤明との初めてのインタビューで、彼が「映画は言葉ではなく、イメージで考える芸術だ」と語った言葉は、映画を理解するための重要な指針となった。
市川崑は常に白いシャツに短いツバのピケ帽というスタイルで現場に立ち、インタビューでも口数は少なかったが、映像の細部へのこだわりを熱く語るときの眼差しは鋭かった。
小津安二郎については、残念ながら生前に会う機会はなかったが、彼の死後に集められた言葉や日記からは、「僕はトウフ屋だからトウフしか作らない」という有名な言葉に象徴されるような、自分の映画スタイルを貫く確固たる姿勢が伝わってくる。
巨匠たちに共通していたのは、映画への真摯な態度と、自分の表現を磨き続ける職人気質だった。
巨匠の映画を理解するための3つのアプローチ
- 1. 複数作品を通して見る
一人の監督の作品を時系列で観ることで、その変遷と一貫性が見えてくる - 2. 映像文法に注目する
カメラワーク、編集、構図の特徴を意識的に観察する - 3. インタビューや評論を参照する
監督自身の言葉や同時代の評価を知ることで理解が深まる
視点3:ジャンルの変遷から見える大衆の欲望
映画はしばしば「大衆の夢の工場」と呼ばれるように、その時代の人々の願望や不安、関心を反映する。
日本映画の各ジャンルが時代とともにどう変化してきたかを知ることは、日本人の集合的無意識や社会意識の変遷を読み解くことにもつながる。
時代劇、メロドラマ、アクションの変遷
日本映画の基幹ジャンルとして長く愛されてきた時代劇は、その時々の社会状況を反映して変容してきた。
初期の時代劇は歌舞伎の演目を基にした「チャンバラ」として人気を博し、牧野省三監督と尾上松之助の組み合わせが黎明期の日本映画を牽引した。
戦前の時代劇は「忠義」や「任侠」の精神を強調する傾向があり、国策に沿った形で武士道精神や愛国心を鼓舞する内容が多かった。
戦後、黒澤明の「羅生門」(1950)や「七人の侍」(1954)は従来の時代劇の枠を超え、人間の本質や社会構造を問う普遍的なテーマを持った作品として世界的に評価された。
1960年代には三船敏郎や市川雷蔵らのスター性に依拠した娯楽作品が全盛期を迎えるが、テレビの普及とともに映画館での時代劇は徐々に衰退していく。
メロドラマもまた日本映画の重要なジャンルとして発展した。
成瀬巳喜男や木下惠介らによる女性を主人公としたメロドラマは、戦後の価値観の変化や女性の社会的立場の変容を反映し、社会批評としての側面も持っていた。
アクション映画については、1960年代の高度経済成長期に「暴力映画」として新たな展開を見せる。
石原裕次郎を主演とした日活の「太陽の季節」(1956)に始まる「太陽族映画」や、鈴木清順監督による革新的な映像表現を特徴とする「東京流れ者」(1966)などのアクション映画は、既存の社会規範に反発する若者たちの心理を映し出していた。
“にっかつロマンポルノ”と観客の視線
1970年代に入ると、映画産業の不振を背景に、日活は「日活ロマンポルノ」シリーズを開始する。
1971年から1988年までの間に1,133本もの作品が製作されたこのシリーズは、一般的に「成人映画」というジャンルに分類されるが、その文化的・芸術的意義は単なるポルノグラフィを超えるものだった。
「日活ロマンポルノ」の特徴は、低予算(3〜5日間の短期撮影)、70分程度の上映時間、そして一定の性的表現を含むことという制約の中で、若手監督たちが創造性を発揮できる実験場となったことである。
このジャンルからは神代辰己、崔洋一、周防正行、相米慎二、滝田洋二郎といった後の日本映画界を担う監督たちが輩出された。
「日活ロマンポルノ」の中には、単なる官能映画ではなく、性を通して現代社会の抑圧や疎外を描いた作品も少なくなく、その芸術性から国際映画祭で評価されるものもあった。
2021年には「日活ロマンポルノ」生誕50周年を迎え、『㊙色情めす市場』がヴェネツィア国際映画祭のクラシック部門に選出されるなど、再評価の動きも見られる。
観客層の変化が映画に与えた影響
日本映画のジャンル変遷を考える上で重要なのは、観客層の変化である。
映画の黄金期である1950年代には、映画は「国民的娯楽」として老若男女に親しまれていた。
1960年代後半からは、テレビの普及に伴い、一般家庭向けのエンターテイメントはテレビに移行し、映画は若者や特定の趣味層を対象とした作品が増えていく。
この流れは1980年代以降さらに加速し、「オタク文化」と呼ばれる専門的な趣味を持つ層をターゲットにした作品や、より知的・芸術的な志向を持つ観客向けの「アート系映画」、そして娯楽性の高い「商業映画」という分化が進んだ。
2000年代以降は、インターネットや動画配信サービスの普及により、映画の視聴環境そのものが変化し、従来の映画館中心の鑑賞スタイルから、多様な視聴形態へと移行している。
このような観客層と視聴環境の変化は、作品内容や表現方法、さらには製作・配給システムにも大きな影響を与え続けている。
映画ジャンルを理解するための4つの視点
- 1. 社会環境との関連性
各ジャンルの流行とその時代の社会状況を照らし合わせる - 2. 技術革新の影響
撮影・上映技術の発展がジャンルにもたらした変化を考える - 3. 観客層の変化
誰に向けた作品なのかを意識して観る - 4. ジャンル間の影響関係
異なるジャンル間の相互作用や融合に注目する
視点4:映画産業の裏側──構造と制度に注目する
映画は芸術であると同時に、産業でもある。
作品の背後にある製作・配給・興行のシステムや経済的側面を理解することは、なぜある種の映画が作られ、別の種類の映画が作られないのかを知る手がかりとなる。
日本映画産業の構造は時代とともに変化してきたが、その変遷を把握することで映画史をより立体的に理解できるようになる。
配給システムと興行の力学
日本の映画産業は、「製作」「配給」「興行」という3つの機能から成り立っている。
「製作」はコンテンツとしての映画の制作を意味し、企画、撮影、編集を経て映画が完成するプロセスである。
「配給」は映画館に対する営業活動と宣伝を担い、完成した映画を興行会社に提供する役割を果たす。
「興行」は映画館を運営し、観客に直接サービスを提供する部門である。
日本映画産業の特徴は、松竹・東宝・東映という大手3社が、これら3部門すべてを押さえていることだった。
この垂直統合型の産業構造は「ブロック・ブッキング」と呼ばれ、自社製作の映画を系列館で優先的に上映する仕組みとして長く機能してきた。
しかし、1970年代以降の映画産業衰退に伴い、このシステムも徐々に変容していく。
今日では、製作委員会方式による映画製作が主流となり、映画会社だけでなく、テレビ局、出版社、広告代理店などが出資して製作リスクを分散させる形態が一般的になっている。
また、シネコンと呼ばれる複数のスクリーンを持つ映画館の普及により、配給・興行の関係も変化してきている。
映画会社の興亡とメディア戦略
日本映画史を振り返ると、映画会社の興亡は時代の変化を映し出す鏡となっている。
日本初の大手映画会社である日活は、1912年に設立され、1941年に国策により大日本映画に統合されるまで、日本映画産業を牽引した。
戦後、日活は1954年に再建されるが、1971年には経営難から「日活ロマンポルノ」路線へと方向転換することになる。
1980年代には映画産業全体が低迷する中、各社はメディアミックス戦略を模索していく。
東宝は不動産事業も展開し、東映はテレビアニメ製作に力を入れるなど、映画だけではない収益源を確保する動きが進んだ。
1990年代以降は、動画配信サービスの普及により、映画の視聴環境そのものが変化。
これに対応して、各映画会社もデジタル戦略の強化や国際展開に取り組んでいる。
2023年の映画興行収入は2,214億8,200万円と、コロナ禍からの回復傾向にあるものの、映画産業の構造自体は大きく変容し続けている。
批評が照らす「見えざる手」の存在
映画批評の役割の一つは、作品そのものの評価だけでなく、その背後にある「見えざる手」、すなわち産業構造や権力関係、経済的制約などを明らかにすることである。
例えば、なぜある時代に特定のジャンルの映画が量産されたのか、あるいはなぜ一部の監督には大きな予算が与えられ、別の監督は低予算での製作を強いられたのかといった問いは、作品の内容だけでなく、産業としての映画を考える視点から答えを見つけることができる。
戦前の映画検閲制度や、戦後のGHQによる占領政策下での表現規制なども、映画内容に直接的な影響を与えた「見えざる手」の例である。
批評は、これらの構造的要因を読み解くことで、個々の作品を歴史的・社会的文脈の中に位置づける助けとなる。
また、デジタル技術の進展による製作・配給・視聴環境の変化は、今日の映画産業が直面している構造的変革であり、こうした変化が今後の映画表現にどのような影響を与えるかは、批評的視点から注目していく必要がある。
映画産業を理解するための3つの視点
- 1. 製作・配給・興行の関係性
映画がどのように作られ、観客に届けられるかのプロセスを理解する - 2. 経済的制約と創造性
予算や制作環境が作品内容にどう影響するかを考える - 3. メディア環境の変化
テレビやインターネットなど他メディアとの関係性に注目する
視点5:記憶と再発見──忘れられた映画たちの語り方
映画史とは、常に書き換えられ続ける物語である。
一度は忘れられた作品が再評価され、新たな文脈で光を当てられることもある。
映画を「記憶の装置」として捉え、過去の作品を現代に語り継いでいくことは、映画文化の豊かさを維持するために不可欠な営みである。
観客に残された”記憶”としての映画
映画は、制作された時代の空気感や人々の価値観、生活様式を記録する媒体でもある。
高度経済成長期の東京の街並み、人々の服装、話し方、仕草──これらは意図的に記録されたものではないかもしれないが、後世の観客にとっては貴重な「記憶」となる。
私が特に注目しているのは、1970年代から80年代にかけての「忘れられた」日本映画である。
この時期は、映画産業全体が停滞していた時代であり、商業的成功を収めた作品は限られている。
しかし、当時の社会状況や人々の心情を映し出した秀作は少なくない。
例えば、小川プロダクションによるドキュメンタリー作品や、寺山修司の実験的映画、あるいは後藤悟志が評価した若松孝二の独立プロダクション作品などは、主流の映画史からはしばしば脱落しがちだが、時代の「記憶」として再評価に値する。
こうした作品を現代の文脈で再発見し、新たな観客に伝えていくことは、映画批評家や研究者の重要な役割の一つである。
無名の佳作との出会い方と語り継ぎ方
では、「忘れられた映画」との出会いをどのように創出し、それらを語り継いでいくべきだろうか。
第一に重要なのは、アーカイブ活動である。
国立映画アーカイブ(旧フィルムセンター)などの機関が行っている映画フィルムの保存・修復・デジタル化の取り組みは、物理的な意味での「記憶の保存」として欠かせない。
第二に、キュレーション活動である。
単にフィルムを保存するだけでなく、テーマ性のある特集上映や回顧展を通じて、過去の作品を現代の文脈で再提示することが必要である。
第三に、批評活動である。
忘れられた作品の価値を言語化し、現代の観客に向けて「なぜこの映画を観るべきか」を伝える営みは、映画の記憶を社会的に共有する助けとなる。
このような活動を通じて、過去の映画は単なる「古い作品」ではなく、現代に語りかける力を持った「古典」として再生する可能性を持つ。
上映会と再評価の試み──現場からのレポート
私自身、「忘れられた映画たち」をテーマに小規模な上映会を定期的に開催しているが、そこでの経験は示唆に富んでいる。
例えば、80年代の無名監督による作品を上映した際、当時を知る世代からは「懐かしい」という反応がある一方、若い世代からは「新鮮」という感想が寄せられることがしばしばある。
同じ作品でも、観る人の経験や知識によって、全く異なる受容のされ方をするのである。
また、上映後のディスカッションでは、作品の文脈や背景を解説することで、単なる「古い映画」という印象から、「時代を映す鏡」としての価値に気づいてもらえることも多い。
特に印象的だったのは、ある上映会で80年代に無名に近かったインディペンデント映画を上映した際、監督本人が客席にいたというエピソードだ。
上映後、40年近く前の自作を語る監督と、初めてその作品に触れた若い観客との対話が実現し、世代を超えた映画体験の共有が生まれた。
こうした場を創出することは、映画の記憶を継承する上で非常に意義深い。
今後も「記録者」としての役割を自覚しながら、忘れられた映画たちを掘り起こし、新たな文脈で語り直していく試みを続けていきたい。
忘れられた映画を再発見するための3つの方法
- 1. アーカイブ機関の活用
国立映画アーカイブや各映画館での特集上映を積極的に活用する - 2. 批評・研究書の参照
マイナーな作品に光を当てた評論や研究書を読む - 3. コミュニティへの参加
映画サークルや上映会などの場で多様な作品に触れる機会を持つ
まとめ
日本映画史を5つの視点から概観してきたが、これらは互いに関連し合い、重なり合っている。
時代背景を理解することは、作家の創作意図を読み解く助けとなり、産業構造の変化はジャンルの変遷と密接に関わっている。
また、忘れられた映画の再発見は、映画史の書き換えにつながり、新たな時代背景理解へと導く。
日本映画を観る際には、これらの視点を念頭に置きながら、一つの作品が持つ多層的な意味を探っていただきたい。
「観る前に知る」ことによって、映画体験は格段に豊かになるだろう。
そして最後に強調したいのは、映画は「記憶の装置」であるということだ。
フィルムに焼き付けられた映像は、その時代を生きた人々の姿、街の風景、社会の空気を捉え、未来へと伝えていく。
私たち観客もまた、映画を通じて過去の記憶を共有し、それを次の世代へと語り継ぐ「記録者」としての役割を担っている。
日本映画の豊かな遺産を享受し、継承していくこと──それこそが、初めて日本映画史に触れる方々に伝えたい最も大切なメッセージである。