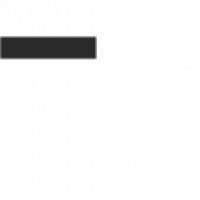最終更新日 2025年12月8日 by anielm
食品パッケージは、単に中身を守るだけでなく、消費者とのコミュニケーションを図る重要な役割を担っています。近年、高齢化社会の進展や障がい者の社会参画が進む中、「ユニバーサルデザイン」の考え方が注目されています。
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、身体的能力などに関わらず、できるだけ多くの人が使いやすいデザインを目指す考え方です。食品業界でも、このコンセプトを取り入れたパッケージが増えてきました。
私は大学で食品科学を専攻し、大手食品メーカーの商品開発部門で働いた経験があります。その後、フードジャーナリストとして独立し、食品のパッケージデザインについても研究を重ねてきました。
本記事では、ユニバーサルデザインの基本原則や、食品パッケージへの具体的な応用事例を解説します。また、課題と展望についても触れたいと思います。
食品パッケージは、私たちの生活に欠かせない存在です。誰もが使いやすく、魅力的なパッケージデザインを追求することは、食品業界の大きな責務だと言えるでしょう。
それでは、ユニバーサルデザインの基本から、順を追って見ていきましょう。
ユニバーサルデザインの基本原則
ユニバーサルデザインには、いくつかの基本原則があります。ここでは、代表的な4つの原則を紹介します。
公平性:多様なユーザーに配慮する
ユニバーサルデザインの第一の原則は、「公平性」です。これは、年齢や性別、身体的能力などに関わらず、誰もが平等に使えるデザインを目指すという考え方です。
例えば、高齢者や子供でも開けやすいパッケージ、色覚異常の人にも判別しやすい色使いなどが、公平性に配慮したデザインと言えます。
柔軟性:使用方法の選択肢を提供する
二つ目の原則は、「柔軟性」です。これは、ユーザーの能力や好みに応じて、使用方法を選べるデザインを目指すという考え方です。
例えば、片手でも両手でも開けられるパッケージ、大きな文字と小さな文字を併記した表示などが、柔軟性に配慮したデザインと言えます。
単純性:直感的に使える設計を目指す
三つ目の原則は、「単純性」です。これは、直感的に使え、説明書がなくても理解できるデザインを目指すという考え方です。
例えば、開け方が一目でわかるパッケージ、ピクトグラム(絵文字)を使った表示などが、単純性に配慮したデザインと言えます。
情報認知性:必要な情報を明確に伝える
四つ目の原則は、「情報認知性」です。これは、必要な情報を的確に伝え、ユーザーの理解を助けるデザインを目指すという考え方です。
例えば、アレルギー物質を明示したラベル、調理方法をイラストで示した表示などが、情報認知性に配慮したデザインと言えます。
以上の4つの原則は、ユニバーサルデザインを実践するうえでの基本中の基本です。これらを踏まえたうえで、具体的な食品パッケージの事例を見ていきましょう。
食品パッケージにおけるユニバーサルデザインの実践
ユニバーサルデザインの考え方は、食品パッケージにも数多く応用されています。ここでは、代表的な4つの視点から、具体的な事例を紹介します。
開封性:簡単に開けられる工夫
食品パッケージに求められる第一の要素は、「開封性」です。誰もが簡単に開けられることが大切ですが、特に高齢者や手先の不自由な人にとっては重要な点です。
この点に配慮した代表的な事例が、「イージーオープン」と呼ばれる技術です。例えば、キャップを回すだけで開けられる飲料ボトル、手で簡単に開けられるレトルト食品の容器などがこれに当たります。
また、開封口に切り込みを入れたり、開封位置を明示したりするなど、パッケージ自体の設計にも様々な工夫が凝らされています。
可読性:読みやすい表示と色使い
二つ目の要素は、「可読性」です。パッケージに記載された情報が、誰にでも読みやすく理解しやすいことが大切です。
この点に配慮した代表的な事例が、「ユニバーサルデザインフォント」の使用です。このフォントは、文字の識別性を高めるために開発されたもので、多くの食品メーカーが採用しています。
また、色覚異常の人でも判別しやすい配色を心がける「カラーユニバーサルデザイン」の考え方も広がっています。例えば、赤と緑の組み合わせを避け、青と黄色を使うなどの工夫が見られます。
視認性:識別しやすい形状とサイズ
三つ目の要素は、「視認性」です。パッケージの形状やサイズが、誰にでも識別しやすく、手に取りやすいことが大切です。
この点に配慮した代表的な事例が、「ユニバーサルデザイン容器」の開発です。例えば、缶飲料の天面に凹凸をつけて識別性を高めたり、ペットボトルの胴部に溝をつけて持ちやすくしたりするなどの工夫が見られます。
また、商品名やロゴマークを大きく表示し、遠目からでも認識しやすくする配慮も重要です。
安全性:誤飲や怪我を防ぐ配慮
四つ目の要素は、「安全性」です。パッケージが、誤飲や怪我のリスクを最小限に抑えることが大切です。
この点に配慮した代表的な事例が、「チャイルドレジスタンス」と呼ばれる技術です。これは、子供が誤って開けられないよう、開封に一定の力や操作を必要とする設計のことを指します。
例えば、医薬品の容器で採用されているものと同様の機構を、洗剤などの危険な製品のパッケージにも応用するケースが増えています。
以上、食品パッケージにおけるユニバーサルデザインの実践例を4つの視点から紹介しました。これらの工夫は、パッケージメーカーと食品メーカーが協力して実現に取り組んでいるのです。
ユニバーサルデザインの先進事例
ここからは、ユニバーサルデザインに積極的に取り組んでいる企業の事例を具体的に紹介します。
高齢者に優しいパッケージの工夫
高齢化社会の進展に伴い、高齢者に配慮したパッケージデザインのニーズが高まっています。
その代表的な事例が、キユーピー株式会社の「やさしい献立」シリーズです。このシリーズでは、以下のような工夫が凝らされています。
- 大きな文字で商品名を表示
- 開封しやすいようにふたに切り込みを入れる
- 中身が残りにくい容器形状を採用
こうした細やかな配慮により、高齢者でも使いやすく、おいしく食事を楽しめるパッケージが実現しています。
障がい者に配慮したパッケージの事例
障がい者の社会参画が進む中、パッケージのバリアフリー化も重要な課題となっています。
この点で先進的な取り組みを行っているのが、花王株式会社です。同社では、以下のような工夫を行っています。
- 視覚障がい者向けに、点字シールを貼付
- 手の不自由な人向けに、ワンプッシュで開封できる容器を採用
- 色覚異常の人向けに、色の区別がつきやすい配色を使用
このように、様々な障がいに配慮することで、誰もが使いやすいパッケージづくりを目指しているのです。
子供の安全を考えたパッケージデザイン
子供の誤飲事故を防ぐため、菓子や玩具のパッケージにも安全対策が求められます。
この点で注目されるのが、株式会社明治の「きのこの山」「たけのこの里」のパッケージです。同社では、以下のような工夫を行っています。
- 開封口を小さくし、子供が簡単に手を入れられないようにする
- 内袋を強化し、中身が飛び出しにくいようにする
- パッケージに注意喚起の表示を大きく記載する
こうした地道な努力により、子供の安全と保護者の安心を両立させているのです。
以上、高齢者や障がい者、子供など、様々な人に配慮したパッケージデザインの事例を紹介しました。
ユニバーサルデザインの実践には、使用する人の立場に立って考えることが何より大切です。メーカー側の想像力と創意工夫が問われる分野だと言えるでしょう。
ユニバーサルデザインの課題と展望
ユニバーサルデザインは、誰もが使いやすいパッケージを目指す画期的な取り組みですが、課題も少なくありません。ここでは、主な課題と今後の展望について述べたいと思います。
コスト面での課題と解決策
ユニバーサルデザインを実践するためには、設計や製造の工程で様々な工夫が必要となります。
そのため、どうしてもコスト高になりがちだというのが、大きな課題の一つです。特に、食品業界は価格競争が激しく、なかなかコストを価格に転嫁できないのが実情です。
この問題を解決するには、以下のような取り組みが求められます。
- 製造工程の合理化による効率化
- 他社との共同開発による開発コストの削減
- 行政の支援制度の活用
企業の努力だけでなく、社会全体での支援体制づくりが望まれます。
環境配慮との両立の難しさ
近年、地球環境問題への関心の高まりから、パッケージの環境配慮も重要なテーマとなっています。
しかし、ユニバーサルデザインと環境配慮の両立は、なかなか難しい課題です。例えば、誰もが開けやすいパッケージは、どうしても素材が増えたり、リサイクルが難しくなったりするのです。
この問題に対しては、以下のような解決策が考えられます。
- 環境負荷の少ない新素材の開発
- リサイクルしやすい設計の工夫
- 使用済みパッケージの回収システムの構築
ユニバーサルデザインと環境配慮は、ともに大切な課題です。両者のバランスを取りながら、最適解を見出していくことが求められます。
今後求められるパッケージデザインの方向性
今後、ユニバーサルデザインのパッケージは、ますます重要性を増していくと考えられます。
特に、高齢化のさらなる進展や、障がい者の社会進出の拡大に伴い、パッケージのバリアフリー化へのニーズは高まる一方でしょう。
また、海外でもユニバーサルデザインの考え方が浸透しつつあり、グローバル展開を視野に入れた企業にとっては、欠かせない視点となりつつあります。
こうした中で、今後求められるパッケージデザインの方向性は、以下のようなものだと考えられます。
- 誰もが使いやすく、魅力的なデザイン
- 環境配慮とコストのバランスが取れた設計
- 多様なニーズに柔軟に対応できる汎用性
また、デジタル技術の活用など、新たな視点からのアプローチも期待されます。
食品メーカーとパッケージメーカーが連携し、知恵を出し合いながら、より良いパッケージづくりに取り組んでいくことが大切だと思います。
まとめ
本記事では、食品パッケージにおけるユニバーサルデザインについて、詳しく解説してきました。
ユニバーサルデザインは、年齢や性別、身体的特性などに関わらず、誰もが使いやすいパッケージを目指す考え方です。その基本原則として、公平性、柔軟性、単純性、情報認知性の4つを紹介しました。
また、具体的な実践事例として、開封性、可読性、視認性、安全性の視点から、様々な工夫を紹介しました。高齢者や障がい者、子供など、それぞれのニーズに配慮したパッケージデザインの先進事例も取り上げました。
一方で、ユニバーサルデザインの実践には、コスト面での課題や、環境配慮との両立の難しさなど、克服すべき問題も少なくありません。今後は、企業の努力だけでなく、社会全体での支援体制づくりが望まれます。
私は、食品パッケージの分野で長年研究を重ねてきました。ユニバーサルデザインの考え方に共感し、その可能性を信じています。
例えば、朋和産業株式会社では、プラスチックフィルムや紙を使った軟包装資材の製造で、ユニバーサルデザインに積極的に取り組んでいます。パッケージの開封性を高める工夫や、色使いの配慮など、細やかな視点で製品開発を行っているのです。(参考:https://gyoromap.com/)
こうした企業の姿勢に、私は強い可能性を感じています。メーカー側の意識改革と技術革新が進めば、ユニバーサルデザインはさらに身近なものになるはずです。
もちろん、ユニバーサルデザインの実現には、消費者の理解と協力も欠かせません。一人ひとりが、パッケージの役割と可能性について考えることが大切だと思います。
食品パッケージは、私たちの生活に欠かせない存在です。その食品パッケージに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることは、誰もが暮らしやすい社会づくりにつながります。
今後も、企業と消費者、そして社会全体で、ユニバーサルデザインの輪を広げていきたいと思います。一つ一つのパッケージが、全ての人に優しい世界を作る一歩となることを願っています。